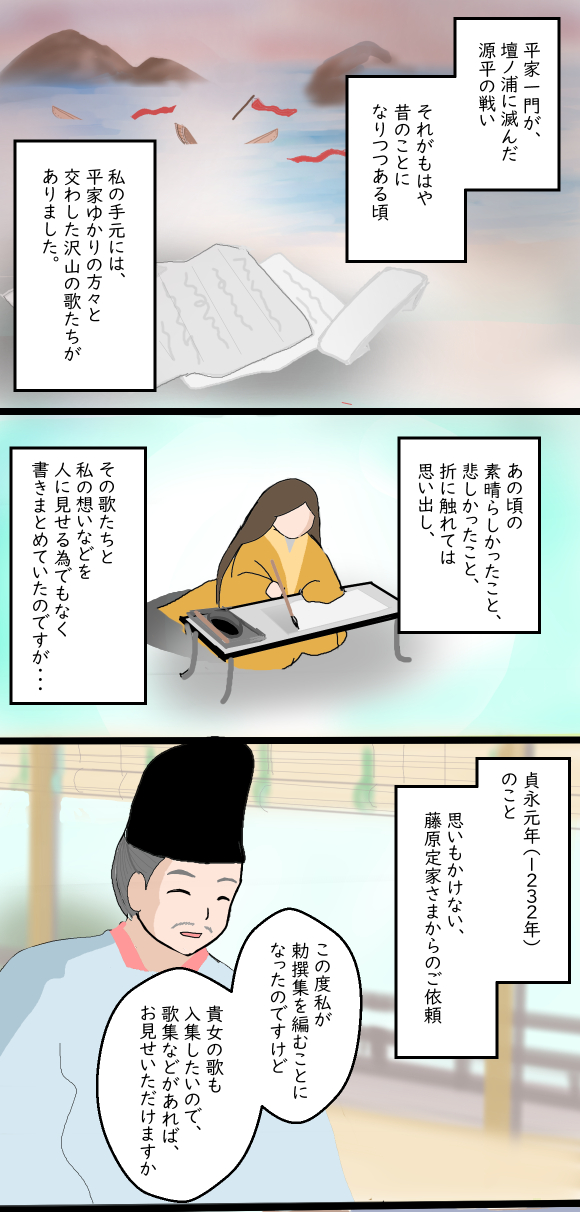大宰府を追われた平家と、平清経の入水【建礼門院右京大夫集あらすじマンガ】|平家物語
都を落ちた平家は、福原の旧都も棄て、九州へ。
あらすじを漫画でどうぞ。
『建礼門院右京大夫集』<206番詞書>より
尊円(そんえん)
右京大夫の異父兄。父は藤原俊成。
現在、右京大夫が身を寄せている。
右京大夫(うきょうのだいぶ)
平徳子(建礼門院)に仕えていた女房。現在は退職。平資盛の恋人。
寿永二年(1183)8月25日、九州に入った平家は、大宰権少弐・原田種直の宿所を、安徳天皇の御在所としました。
大宰府は、平家の日宋貿易の拠点。
平家は、大宰府を拠点として勢力を回復させるつもりでした。
ところが、豊後国の知行国主・藤原頼輔が、平家を追討することを決めてしまいます。このとき、平家追討を命じられたのは豊後国の豪族・緒方惟義(維義・惟栄)でした。
緒方惟義は、かつて重盛と主従関係にあったので、資盛が説得に向かいますが受け入れられず、結局平家は大宰府からも撤退せざるを得ませんでした。
『平家物語』では、緒方惟義を説得する役目に資盛が抜擢された理由として、惟義が重盛の家人であったことをあげています。
ですが、都落ちあたりの資盛の動向を踏まえると、資盛はいまだ後白河院の元への帰降を諦めておらず、惟義と(神器返還も含めた)和平の折衝に臨んでいたのではないか、という説もあります。
こうした中で、弟・清経の入水という悲劇が起こります。
柳ヶ浦を追われたとき、早くも前途を悲観し、自ら入水した公達がいます。
資盛のすぐ下の弟、平清経(たいらのきよつね)です。
『平家物語』によれば、清経は、
と言って、
『平家物語』は清経を「何事も思ひいれたる人」(なんでも思いつめる性格の人)と評していますが、
後の平家の公達の悲劇を思うと、清経の見通しは間違っていなかったといえますね。
このとき、清経はまだ21歳でした。(満19~20歳)
あらすじを漫画でどうぞ。
『建礼門院右京大夫集』<206番詞書>より
登場人物
右京大夫の異父兄。父は藤原俊成。
現在、右京大夫が身を寄せている。
右京大夫(うきょうのだいぶ)
平徳子(建礼門院)に仕えていた女房。現在は退職。平資盛の恋人。
福原→大宰府→そして屋島へ
寿永二年(1183)8月25日、九州に入った平家は、大宰権少弐・原田種直の宿所を、安徳天皇の御在所としました。
大宰府は、平家の日宋貿易の拠点。
平家は、大宰府を拠点として勢力を回復させるつもりでした。
ところが、豊後国の知行国主・藤原頼輔が、平家を追討することを決めてしまいます。このとき、平家追討を命じられたのは豊後国の豪族・緒方惟義(維義・惟栄)でした。
緒方惟義は、かつて重盛と主従関係にあったので、資盛が説得に向かいますが受け入れられず、結局平家は大宰府からも撤退せざるを得ませんでした。
大宰府を落ちた平家は、豊前国柳ヶ浦に拠点を置こうとしますが、ここも追い出され、讃岐屋島へ移りました。
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
ですが、都落ちあたりの資盛の動向を踏まえると、資盛はいまだ後白河院の元への帰降を諦めておらず、惟義と(神器返還も含めた)和平の折衝に臨んでいたのではないか、という説もあります。
結局この交渉は決裂し、平家は九州から去らねばならなくなるのですが、もしも資盛がいまだ帰降を望んでいたのだとすれば、主戦派である平家主流と、小松家の間には軋轢があったのではないかという想像もできます。
平資盛と緒方惟義の交渉は、えこぶんこ2で詳しく解説しています。
(別ウィンドウが開きます)
(別ウィンドウが開きます)
こうした中で、弟・清経の入水という悲劇が起こります。
平清経の入水
資盛のすぐ下の弟、平清経(たいらのきよつね)です。
『平家物語』によれば、清経は、
と言って、
月の夜に柳ヶ浦の海上で、船から身を投げたといいます。
『平家物語』は清経を「何事も思ひいれたる人」(なんでも思いつめる性格の人)と評していますが、
後の平家の公達の悲劇を思うと、清経の見通しは間違っていなかったといえますね。
このとき、清経はまだ21歳でした。(満19~20歳)





 えこぶんこ2
えこぶんこ2

 ←新しい記事
←新しい記事 前の記事→
前の記事→